新人教育をするとき、
あまり言いすぎてやめられたら困るので、
言いたいことが言えなくてストレスがたまるのです。
どうしたらいいですか?
こういった相談を受けることがあります。
このような相談を受けたときは必ず
「そのストレスは、心理の専門家が作った常識が原因です。ごめんなさい。」
こう謝罪してから相談をお受けしています。
なぜかというと…
それを解説します。
心理の専門家が作った常識
心理の研究結果から、以下の常識が導きだされました
- 行動や学習は本人の感じ方や考え方によって起こるもので、外からコントロールできるものではない。
- だから、外から見えない内面的なこころの働きを重視する。
- そして、外から見えないこころを重視するのだから、本人のペースを尊重すること。
要するに、
「学ぶ気がなければ、学ばせることはできないから無理強いをしてはいけない」
ということです。
これは、研究結果から導き出されたことですから間違いはありません。
でも、これを過大解釈した心理の専門家を名乗る人たちが、
- 本人のペースを尊重しないことはこころを軽視することになる
- それは、こころを傷つけることにつながる。
- だから、本人のペースを尊重して、こころを傷つけるようなことはしないように
こんなもっともらしい常識を作り上げてしまったのです。
意欲を高めることはできるはず
本当に本人がやる気を起こすまで行動や学習を促すことはできないのでしょうか?
ここでいう学習とは、これから先の行動や考えに変化を起こすような知識の獲得や経験のことです。
それなら、未知なることへのチャレンジ意欲を高めることで、学習や行動を促すことは可能のはずです。
チャレンジの意欲は
・失敗したとしても乗り越え方を一緒に考えてくれる人がいる
・チャレンジの背中を押してくれる人がいる
そのことによって高まります。
でも、未知なることへのチャレンジは、不安を伴います。
そのため、「ネガティブな感情を持つことはこころを傷つけること」という
心理の専門家を名乗る人たちは、チャレンジもさせてくれないのです。
チャレンジは好循環をつくる
チャレンジして課題を乗り越えるには、困難がつきものです。
そして、人を育てる立場になったときは、その困難に一緒に向き合うことになります。
そのため 「人を育てるということが自分を育てる」ということになることも多いのです。
チャレンジさせないのは保身のため
チャレンジさせる課題が困難であるほど、自分も困難な体験をすることになります。
人を育てる立場ですからそれを受け止め、一緒に困難を乗り越えていければいいのですが…
もし、自分に余裕がなかったり、困難への立ち向かい方がわからなかったらどうすればいいでしょうか?
一番簡単なのは、課題にチャレンジさせないことです。
「無理しなくていいよ」「できるところまででいいからね」とチャレンジさせなければお互いに困難な体験から逃れることができるからです。
まとめ
心理の専門家を名乗る人たちが作った常識がもとになって、
・「無理しなくていいよ」
・「できるところまででいいからね」
こういった言葉が人を育てる場で使われることが増えたように感じます。
でも、人を育てる場で使われる
・「無理しなくていいよ」
・「できるところまででいいからね」
こういったという言葉の多くは、相手のペースを尊重した言葉ではなく、
自分を守る保身の言葉であることが多いのです。
人を育てる立場になって行動や学習を促すためには、
自らも困難に立ち向かう余裕と困難を乗り越える知恵が必要になります。
まずは、自分の意欲を高めるために、
・失敗したとしても乗り越え方を一緒に考えてくれる人
・チャレンジの背中を押してくれる人
を、身の回に探して確保しておきましょう。
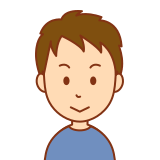
この記事が、
もっと素敵な明日に向かう今日のために
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
ご訪問ありがとうございました。
SNSのフォローもしていただけると嬉しいです。


コメント