身近な人が社会生活をできないでいる。
「どうにかしてあげたいが、どうしたらいいかわからない」
こういった相談が増えてきました。
ひきこもりじゃなく「こもり人」と言いましょう。
こんなルールができたところで、こもった人が社会に出られるわけではありません。
それを痛感している人たちが、相談に来られるのです。
こもる状態におちついてしまう
こもることを選択するのには、何かきっかけが存在します。
でも、
・何がきっかけになったのかを説明できるようになるには長い時間が必要であったり、
・どれだけ時間をかけたとしても説明できるようにならない人もいらっしゃいます。
また、ひきこもりは、「本人の問題」という人がいたり、「社会の問題」という人がいたりして、何が正しいのかわからないというのが実際のところだと思います。
多くの関連書籍やメディアの報道では
「タイミングが来れば社会に出ていけるようになる。だから、本人が社会に出る気がおこるまで待つ」
こういうサポートが基本とされています。
ただ、こもる時間が長くなるほど社会復帰が難しくなるという現実があります。
実際に、こもっている本人の話を聞いてみると、
・自分のペースでやらせてほしいといいながら
・どうしたらいいかわからなくて困っていることが多く
こもっている人が家族の中にいるという方に話を聞いてみると、
・この基本があっていれば、こもっている人が減っていてもいいはず
と、この基本に疑問を持っている人が多いのです。
それでも、どうしたらいいかわからないから、
本人の意思を尊重した、ひきこもるという状態におちついてしまっているのです。
こもるきっかけは喪失感
こもるきっかけを紐解いていくと、その多くが、「社会の中での自分の居場所を失った感覚」です。
卒業や進学、就職や退職、事故や病気などの大きな変化は居場所の変化につながるので居場所を失った感覚が生まれるのはイメージしやすいと思います。
ただ、感じ方は人それぞれです。
そんなこと?と思うようなことでも自分の居場所を失った感覚は起こってしまうのです。
例えば、
・仲がいいと思っていた友達に嫌味を言われた
・レギュラーで頑張っていたのに補欠になってしまった
・先輩と言い合いになって居づらくなった
などです。
喪失感との向き合い方
自分の居場所は自分らしくいられる場所でもあります。
だから、それを失ったと感じたとき、
「どうしたら自分らしくいられる場所を作れるだろうかと考える人」…Ⓐと、
「どこに自分らしくいられる場所があるのだろうかと考える人」…Ⓑがいます。
Ⓐの人は、今いる社会で自分らしくいられる方法を考える人ですから、いろいろと試行錯誤します。
試行錯誤するのは大変ですが、それをしているうちに今いる社会で自分らしくいられるようになっていきます。
Ⓑの人は、今いる社会以外で自分らしくいられる場所を探す人です。
試行錯誤する必要がないので、負担は少ないですが、環境に自分らしさを委ねることになります。
そのため、自分らしくいることができない環境への不満が強まってしまいまうことがあるのです。
居場所を求めているのに不安で動けない
自分の居場所がなくなったと感じているときは、自分の強みがわからなくなってしまっています。
この状態は、何もできることがないというぐらい自信がありません。
だから、何をするにしても不安が出てきてしまいます。
不安は逃げようとすると追ってくる-不安の正体を知っていれば不安は怖くない-を引用します。
不安は逃げようとすると追ってくる-不安の正体を知っていれば不安は怖くない- https://hoshinob.com/emotion/anxiety
不安には、試験とかマラソンのタイムとかのように自分の力が結果に影響するから不安になるというものと、クラス替えとかくじ引きのように結果を自分の力でコントロールできないから不安になるというものがあります。
自分の力が結果に影響するものであれば、過去問を解いたり、練習をたくさんするなどいろいろな場面を想定しながら準備をすることができます。
だから、自分の力が結果に影響するものは準備できる不安ということです。
準備できるはずなのに準備をしていなければ、直前になって不安が大きくなってしまうのは普通のことですよね。
だから、不安になりやすい人ほど、準備が大切なのです。
そして、全て準備できることばかりではないということも知っておく必要があります。
クラス替えとかくじ引きのように「結果を自分の力でコントロールできないから不安になる」というものがあります。
どんなにシミュレーションをしたとしても、結果が出るその場になってみないと何が起こるかわからない。
つまり、事前に具体的な準備をできることがないという不安です。
結果を自分の力でコントロールできないこの不安をどうにかしようとするということは、コントロールできないはずのことを自分の力でコントロールしようとすること。
ですから、どんなに頑張ったとしても努力の無駄遣いになってしまいますよね。
この不安は、コントロールできないけどその結果を受け止める準備ができているかを確認しているのです。
こもっている状態は、自信がない状態です
ひきこもりから脱して社会に出ていくには
・社会で自分らしくいられる自信より
・自分らしくいる場所を確保するために試行錯誤する
それをつづけるための自信が必要です。
行動する人と行動できない人の違い―口癖は思考の癖をつくる― を引用します。
行動する人と行動できない人の違い―口癖は思考の癖をつくる― https://hoshinob.com/human-resource/habit
ないことを目指すのは、
何か変化が起こってはいけない、変化を起こすようなことをしてはいけないと、現状に踏みとどまり耐えるような頑張りです。
だから、現状に留まることができたことに安心にすることはできても、理想の「ある」に向かって変化していくことの喜びを得ることは難しいのです。
理想の「ある」に向かって変化していくことに喜びを得る人生を歩む人たちの言葉は、「こうしたい」「こうなりたい」「こうだといいな」「こうしてほしいな」など、ほとんどが肯定語で構成されています。
一方、現状に留まることで安心する人生を歩む人たちの言葉は、「こうしたくない」「こうなりたくない」「こうなったら嫌だな」「こうしてほしくないな」など、多くの言葉に否定が含まれています。
どんな人生を歩むのかは、その人の口癖によるものであることも多いのですが、その口癖を作ってしまう周囲の声掛けや態度も影響していることを覚えておきましょう。
変化を起こそうとすれば不安になります。
不安が続けば不快にもなります。
変化するときにこのような気持ちになるのは自然なことです。
でも、周りにいる人が
「本人の不快になることはしない、本人が不安になる刺激は与えない」
こういう姿勢でいると、
不安そうにしたり不快を感じそうなことを避けさせてくなってしまいます。
それが変化を阻むことにつながってしまうこともあるのです。
小さな成功体験を積み上げるしかない
自信がないことから生じた不安は、いつになったら感じなくて済むようになるのでしょうか?
ただ待っていれば、自信をつけていくことができるのでしょうか?
「ない」を目指したとしてもそれは問題を先送りにするだけです。
「ある」を目指して小さな成功体験から自信をつけていくしかありません。
だからこそ、可能性を信じてくれる環境が必要になります。
たとえうまくいかなかったとしても、
・次に頑張るためにどうしたらいいのかを一緒に考えてくれたり
・励まし続けてくれる環境です。
そのような環境の中で、小さなハードルを乗り越えることにチャレンジする。
それが、社会とつながる勇気が作ってくれるのです。
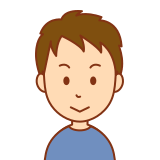
この記事が、
もっと素敵な明日に向かう今日のために
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
ご訪問ありがとうございました。
SNSのフォローもしていただけると嬉しいです。


コメント